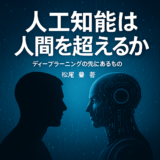こんにちは。
今回は、「ゼロトラスト」というIT用語について、わかりやすくまとめていきたいと思います。
想像してみてください。あなたが勤めている会社のビル。
社員証をかざせば中に入れます。
でも、もし一度入ったら、社長室にも金庫室にも入れてしまうとしたら…ちょっと怖くありませんか?
実は、これまでのITセキュリティは、
まさにそんな感じでした。
「一度ログインできたら、その人は社員だから大丈夫」という前提で、
社内ネットワークの中はゆるくなっていたんです。
でも、それだと、もしも一人のアカウントが乗っ取られたら、
その人になりすましてやりたい放題。
そんな時代に登場したのが、「ゼロトラスト」という考え方です。
「誰も信用しない。だから、毎回ちゃんと確認する。」
このような考え方がゼロトラストです。
「Zero(ゼロ)」=信用ゼロ
「Trust(トラスト)」=信頼
つまり、「最初から誰も信用しないよ」というちょっと冷たい(?)セキュリティモデルなんです。
でもこれ、ある意味とても合理的。
なぜなら、現代は在宅ワークやノマドワークなど働き方も多様化して、ネット環境も様々で、信じてばかりでは自分の身を守れませんから。
- 社員が自宅のWi-Fiから会社のデータにアクセス
- ノートPCをカフェに持ち出して業務
- 個人のスマホで社内チャットを見る
こんな日常、いまや当たり前ですよね。
でも、昔ながらの「社内は安全」という考えのままだと、こういうアクセスを許可すること自体がリスクになります。
そこで、ゼロトラストでは、
- その人が本当に本人か?
- どこからアクセスしているのか?
- いつもと違う動きではないか?
- アクセスしようとしている情報は適切か?
…をリアルタイムで判断し、問題があれば即ストップする仕組みをとっています。
ゼロトラストは、ATMでお金を引き出す時に毎回暗証番号を入れるのと同じ感覚です。
「私はこの口座の持ち主です」と、毎回ちゃんと照明する。
それって実は、お金を守るための安心の仕組みですよね。
ゼロトラストもそれと同じ。
「なりすましを防ぐ」
「怪しい動きはブロックする」
そうすることで、情報やシステムを守ります。
実はこのゼロトラスト、GoogleやMicrosoftといった世界のIT企業もすでに導入しています。
特に、テレワークが一般的になってからは、会社の外からアクセスする機会が増えました。そのため、「中にいる=安全」では通用しないことがより明確に。
だからこそ、どこからでも安全に働ける仕組みとして、ゼロトラストが広がっています。
これからの時代は、「仲間だからOK」ではなく、
「仲間でもちゃんと確認」が当たり前になります。
ゼロトラストは、信用しないことから始まる
本当の安心を作るセキュリティの考え方です。
イメージとしては、ゼロトラストってATMみたいなものだよね
と覚えたらばっちりかなと思います!